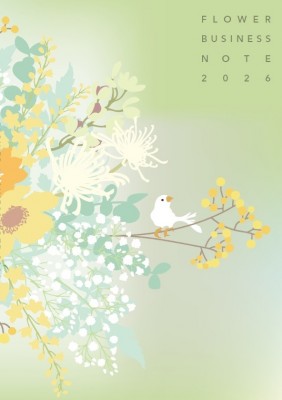花研コーヒーブレイク
花研コーヒーブレイク
“文化の秋”に思う地域の行事とつながりの大切さ
2025.09.10
こんにちは、ゲストブロガーのプロテアです。
9月になり、まだ暑さは残るものの、ふとした瞬間に秋の気配を感じることが増えてきました。皆さんは「秋」と聞くと、どんなイメージが浮かびますか? 「読書の秋」「食欲の秋」「芸術の秋」など、秋にはさまざまな表情がありますね。今回はその中から「文化の秋」にまつわるお話をしたいと思います。
私の生まれ育った地域には、ちょっとユニークな秋の行事が継承されています。十五夜や十三夜に行われる「ぼうじぼ」という行事です。子どもたちが夜に地域の家々を回り、「ぼうじぼあたれ~♬」と歌いながら、藁で束ねた棒状の「ぼうじぼ」で地面を叩き、五穀豊穣を祈ります。そのご褒美としてお菓子やお小遣いをいただける、子どもたちにとってはとても楽しみな行事です。
調べてみると、この行事は栃木県や茨城県の一部地域で受け継がれているとのこと。両県は隣り合っていることも関係していますが、もう一つ面白い背景があります。十五夜は「芋名月」、十三夜は「栗名月」との異名があるように、栃木はサトイモ、茨城は栗の名産地。地域の主要作物の豊作を願う心から、この行事が生まれたのではないかと考えられます。
さらに、「ぼうじぼ」の歌にも地域ごとの違いがあります。私の地元では「ぼうじぼ当たれ、さんかくぶって、そば当たれ」という歌詞でした。「さんかくぶって」とは「三角畑」の訛りと思われます。そばが歌詞に登場するのは、そばの栽培が盛んだった土地柄を反映しているのでしょう。ほかの地域でも大まかには同じ歌詞で、「そば」が大麦や小麦、山芋などに変わるようで、まさにその土地の主作物と結びついた豊作祈願の歌だったのだと感じます。
この行事、残念ながら私の地域でも子どもの数が減少してきたこともあり、継続が難しくなってきています。しかし「ぼうじぼ」のような行事は、地域の特色を体感できるだけでなく、人と人とのつながりを育み、礼儀や社会性を学ぶ場にもなっていました。地域活性の一助ともなる、とても貴重な文化だと改めて思います。
皆さんの地域にも、少しずつ姿を消しつつある文化や行事があるかもしれません。しかし、それを継承することは、地域コミュニティを豊かにし、そこに関わる人の成長にもつながります。11月には「文化の日」もあります。この機会に、自分の地域や季節に根づいた文化を調べたり、実際に参加してみたりするのはいかがでしょうか。小さな一歩が、未来へと文化をつなげる大きな力になるのかもしれません。
ごきげんよう。
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
フラワービジネスノートは9月15日発売です。これがあれば十五夜と十三夜の日付もばっちり確認できます。