 花研コーヒーブレイク
花研コーヒーブレイク
ブログを見てくださったあなただけに『フラワービジネスノート2026』新ポイントを紹介します
2025.09.08
こんにちは。みんなの花研ひろばです。
発売まであと1週間。9月15日発売予定の『フラワービジネスノート2026』の新しいコーナーとポイントをご紹介したいと思います。
★新しいコーナーは大きく3つ!
・「花き購入頻度」推移掲載→Data5をご参照ください
花きの購入金額の減少については毎年紹介させていただく通りですが、実はその背景には経済環境ばかりではなく、一世帯当たりの花きの購入頻度が減少していることが挙げられます。そこで、どのように購入頻度が減少しているのかをグラフでご覧いただきたいと思います。
つまり、お客様の購入単価ではなく(もしくは単価ばかりでなく)、購入単価は低くても購入頻度を上げていくことが花き文化の活性化には欠かせないのではないでしょうか。
生活者にとって興味深い売り場を作り、少しでも興味を持って足を運んでいただくためのアイデアは、マンスリーカレンダーの右側にご紹介しています。併せてご参照いただければ幸いです。
・「小売物価指数」推移掲載→Data6をご参照ください
小売物価指数推移コーナーを新設しました。
物価の情報が叫ばれて久しくなりますが、花の小売り価格はどうでしょうか。
2020年を基点とし、エネルギーも含めた全体の小売物価指数に対し、花(切花、鉢物、バラ、キク、カーネーション)がどのような小売価格の変動を起こしているのか、これをご覧になれば一目瞭然です。
・MONTHLY FLOWERS 枝物追加10品目→マンスリーカレンダー最下部をご参照ください
枝物への注目度アップを受け、マンスリーカレンダー最下部の「Monthly Flowers」のコーナーに「枝物」専用のコーナーを新設しました。これまでは「切花」コーナーに内包されていましたが、今年はそれぞれの月にお勧めの旬のアイテムとして切花10品目・枝物10品目、鉢物5品目をご紹介しています。
そして以下のような思いとともに、『フラワービジネスノート2026』を制作いたしました。同書の「ごあいさつ」からの引用です。
★花研からのメッセージ
「世界経済は今、地政学的な対立や保護主義の台頭によって、分断の傾向が強まっています。その現象はグローバルな視点に立った時ばかりでなく、足元を見れば日本国内、あるいは身近な産業でも起きているように思います。
かつては売れていた商品が売れにくくなる、あるいは事業環境が少しずつ変化し苦しい状況が続くと、どうしても保守的になり、部分的な視点にとどまりがちです。すると、全体的な連携を見失いがちになり、サプライチェーンの再構築や縮小、産業全体の成長鈍化といった影響が懸念されます。
ところで、『リービッヒの最小律』という法則をご存じでしょうか。植物の成長や収量は、必要な栄養素の中で最も不足しているものの水準まで制限されるという法則です。どんなにほかの栄養素が十分にあっても、植物の成長は最も少ない栄養素のレベルまでしか成長しないというものです。
この法則は、花き産業にも通じるところがあるのではないでしょうか。たとえば、物流機能が縮小すれば、どれだけ商品が豊富にあっても運べる量に限界が生じます。あるいは、物流の体制が整っていても、需要が低ければ産業の規模は拡大しません。すなわち、サプライチェーンの中で最も弱い部分が、業界全体の成長を制限してしまうのです。
今後、花き産業が成長していくためには、サプライチェーンを俯瞰してみた課題を共有し、連携して取り組む姿勢が不可欠です。今、私たちが真に危惧すべきは、サプライチェーンの“ミスマッチ”や“分断”です。産業の持続性を確保し、発展を図っていくためには、全体最適を志向して力を尽くすことが、ますます重要になるでしょう。
本書が、そのような連携と協働を後押しし、花き産業の未来をともに考える一助となれば、これ以上の喜びはありません。どのような時代にあっても、業界に関わるみなさまの知恵と行動が、道を切り開きますようお手伝いできれば幸いです。」
このような思いをもとに、今回のフラワービジネスノートを制作いたしました。共感いただける方、あるいはそうでない方におかれましてはそんなページは切り取っていただき、ぜひご利用いただけますと幸いです。
ご予約を承っております。9月15日以降、順次発送させていただきます。
15日は祝日にあたるため、16日以降に発送させていただく場合もございます。
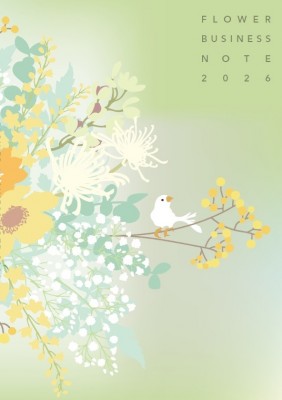
どうぞよろしくお願い申し上げます。










