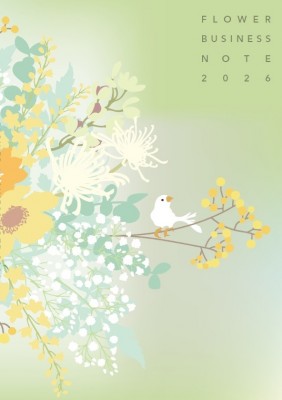花研コーヒーブレイク
花研コーヒーブレイク
キュレーターのいるところ
2025.08.21
花研の一研究員です。
さて、お盆休み中に新潟の糸魚川にある博物館(フォッサマグナミュージアム)に行った話を当ブログにて紹介いたしました。
その博物館の中には、ヒスイの鑑定やら化石の鑑定をしてくれる専門家がいらっしゃいます。糸魚川や博物館敷地内の化石発掘コーナーで見つけたヒスイや化石を持って行くと、それが本物かどうかを鑑定してくれるのです。いいですね。
博物館で働く専門の方は日本では「学芸員」というと思いますが、英語では「キュレーター(curator)」と言います。美術館の専門家も「キュレーター」と言いますね。
キュレーターとはつまり鑑定できる人、目利きということです。目利きがいませんと、評価ができない分野やモノはたくさんあり、博物館や美術館hまさに目利きが活躍する場です。
フォッサマグナミュージアムでも“化石探し”なる体験ができるところがあります。博物館の中庭に白いっぽい石が多数おいてあり、その石を割ると化石が見つかるイベントをやっているのですが、それらしきものを見つけたとして、それは化石なのかどうか、その価値付けがこのイベントの肝になります。つまりは鑑定できる人がいることが重要なのです。素人ではさっぱりわかりません。
その採掘場にある石は、新潟の黒姫山から掘り出した石灰岩で、造山活動で2-3億年前の地層が表面に出てきたものです。握り飯ぐらいの石灰岩をトンカチでたたくと、脆い石灰岩は子供でも簡単に割ることができます。その断面をよくみると化石があるのです・・・あることがあるのです。
しかし、それは本当に化石かどうかはっきりわかりませんので、これかなーと思ったら専門家に鑑定してもらいます。すると「これは海ユリですね」とか「珍しい三葉虫のようですね」などと教えてくれます。まさに目利きという機能が発揮されているのです。
そのうちだんだんと素人発掘家もわかるようになって自分であれこれ見出すことができるようになります。このように目利きが価値を定め、広く目利きの手法を教育していくことがフォッサマグナミュージアムでは機能していました。
翻って、花き市場を考えますと、セリ人や販売に携わる営業部門の方々はみなキュレーターと言えるのではないでしょうか。
例えばですが、(市場にとっての)お客様ごとに品揃えのご要望が違うわけですから、数多くの品目品種、規格、生産地の中から最適なアイテムを選んでご提案します。お店の立地やお客様層、店頭の様子を考慮して提案するわけですから、お客様に対する理解と目利きのスキルが欠かせません。
また、逆からの思考もあって、出荷物に対してふさわしいお客様をご紹介することも多々あります。商品の価値を評価、理解した上でのマッチングですね。一般的にはこれらをセリ人や営業員が行いますが、そうなるとセリ人や営業員をキュレーターと呼んでいいのではないでしょうかと。
ちなみに、わたくしが発掘した化石には、激レアの三葉虫のかけらが入っていたようで、とてもうれしく思いました。
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
既にご予約をいただいているお客様につきましては、発売日以降順次発送してまいりますので、いま暫くお待ちいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
それではみなさま、ごきげんよう。