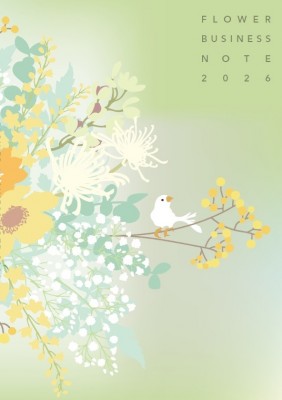花研コーヒーブレイク
花研コーヒーブレイク
レウコとレプト ~混乱はつづくよ、どこまでも~
2025.08.20
こんにちは。みんなの花研ひろばです。
本日はまた妙なタイトルですが、「れう子さん」と「れぷ斗君」ではありません。
大先生のみなさまには笑われてしまいますが、よろしければお付き合いくださいませ。
植物の学名を調べていると、やたら似た名前が登場して「どっちだっけ?」と混乱することがしばしばあります。必要に迫られないときちんと確認せぬままつい流してしまい、あとでモヤモヤが残ることも。
例えば、「レ※▲~スペルマム」っていう学名があったな~くらいで、あれ「レウコスペルマム」だっけ?いや「レプトスペルマム」でしたか??はたして、どちらが正しいのか、もしくは何の植物の学名だったかも覚えられず、暫くもやもやと整理できずにいました。
ある調べ物をしていた時に、ネイティブフラワーの学名に「レウコスペルマム」も「レプトスペルマム」も両方あることがわかり、なるほどこりゃ混乱するわけだと納得。
★レウコスペルマム(Leucospermum)
- ヤマモガシ科、いわゆる「ピンクッション」
- 南アフリカ原産
- 語源:leuco(白い)+spermum(タネ)
- 開花後に白い種子をつけることから。
★レプトスペルマム(Leptospermum)
-
ギョリュウバイ科、ワックスフラワーの仲間
- 南アフリカ原産
-
語源:lepto(細い)+spermum(タネ)
-
種が縦長で細いことに由来。見てみると「柿の種」を小さくした感じです。
なるほど、ひとまずこれに関しては混乱が整理できました。
実は、こんなふうに学名が混乱してしまった例はほかにもあります。例えば、お恥ずかしながら暫くの間「エキノプス」(ルリタマアザミ)のことを「エキノプシス」(サボテンの一種)と覚えていました。全く異なる植物の分類でありながら、学名もその由来も似ているのです。
★エキノプス(Echinops)
・キク科ヒゴタイ属、ルリタマアザミなど
・ギリシャ語で「ハリネズミ」を意味する「 エキノス 」と「外観」を意味する「オプス(ops)」に由来
★エキノプシス(Echinopsis)
・サボテン科エキノプシス属
・ギリシャ語で「ハリネズミ」を意味する「エキノス」と「外観」を意味する「オプシス(opsis)」に由来
いずれも「ハリネズミに似た外観」の意味からつけられたのようなのですが(それ自体はすこぶる納得)、opsかopsisの違いだけってことですな。いやもうここまでくるとギリシャ語でも真剣に学ばない限りは、opsとopsisは何が違うのかわかりません。
ところで、「スペルマム」シリーズと言えば、「カスタノスペルマム」というのがあります。
★カスタノスペルマム(Castanospermum)
・マメ科カスタノスペルマム属
・オーストラリア原産
・「ジャックと豆の木」とか「オーストラリアビーンズ」などの別名でも流通している観葉植物
・ギリシャ語で「kastanea(クリ)」+「sperma(種子)」、種子がクリに似ていることに由来。
※「カスタノ-」とあると、カスタネットと何か関係がありそうな気配あり。カスタネットはその形が栗の実に似ていること、またかつては栗の木からできていたことに由来して、カスタネットという名前になったのだとか。
「スペルマムシリーズ」その2
★オステオスペルマム Osteospermum
・キク科オステオスペルマム属
・南アフリカ(とりわけケープ地方)原産
・osteoが「骨」の意味なのだそうで、bone(骨)+seed(種)からの命名だそうです。タネが骨のように固いことに由来しているのだとか。
「スペルマムシリーズ」その3
★ステレオスペルマム
オステオスペルマムとくれば、早口言葉のようですがステレオスペルマム。
・ノウゼンカズラ科ラデルマケラ属
・学名はRadermachera sinica(ラデルマケラ・シニカ)。原産地は中国南部や台湾。
あら、学名が変わったのかな。スレテオ(stereo)とはギリシャ語で「固い」という意味だそうなので、ステレオスペルマムのタネが固いことからそう呼ばれて、のちに学名が変わったのかもしれません。わかりません。推測です。
ん?ラデルマケラ・・・?
似た名前で「ラデマキア」ってなかったっけ・・・とふと頭をよぎります。
ラデマキアの学名を調べたら、Radermachera sinica(ラデルマケラ・シニカ)でした。つまりラデルマケラとラデマキアとステレオスペルマムは同一植物を指すのでした。
やんやこしいの~。学名の混乱は続くよどこまでも・・・
フラワービジネスノートは9月15日発売です。どうぞよろしくお願いいたします。
それではみなさま、ごきげんよう。